所長挨拶
(元素科学国際研究センター 先端無機固体化学)教授

化学研究所は、「化学に関する特殊事項の学理及びその応用を究める」という設立時の理念を念頭に置きながら、常に時代の変革に柔軟かつ積極的に対応することにより、多様な先駆的・先端的な研究を展開してきました。その絶え間ない活動と発展の歴史は1年半後には100年に届こうとしています。改めてその歴史と伝統へ敬意を表するとともに、先人のこれまでの多くの成果を基に、より豊かな未来を創るための最先端科学の発展に向けて一層の努力をしていく所存です。
現在、化学研究所は5研究系(物質創製化学・材料機能化学・生体機能化学・環境物質化学・複合基盤化学)と3附属センター(先端ビームナノ科学・元素科学国際研究・バイオインフォマティクス)を組織し研究活動を行うとともに、理学・工学・農学・薬学・医学・情報学の6研究科11専攻の協力講座として京都大学の教育と若手人材育成にも貢献しています。この組織体制での運営が十分に機能してきたことは、近年の幾つもの大型研究費の獲得や産学共同研究への展開、そして多くの教職員や学生の顕彰でも実証されています。さらにこれらの基盤的研究教育活動は国際共同利用・共同研究を推進する「化学関連分野の深化・連携を基軸とする先端・学際グローバル研究拠点」活動として一層発展し、多くの国際共同研究成果や若手の国際交流実績を生み出してきました。
しかしながら、ほんの数年前には想像すらできなかったような社会の急激な変化や技術の各段の進歩を目の当たりにし、改めて今まさに必要な組織と運営を考え直す時期に来ているのではないかと痛切に感じています。折しも、日本の研究教育の現状を打破するために、国が提案する国際卓越研究大学構想の下、京都大学でも国際競争力をもった研究・教育機関であり続けるためのさまざまな組織改革が検討されています。化学研究所でも、将来の社会発展と未来の科学技術を見据えて、これからの世界の中で果たすべき役割を含めて、改めて幅広い視点から議論する時期が来ていると感じています。
このような中で、化学研究所がこれまでの長い歴史の中で果たしてきた役割を振り返ってみることは時として重要です。いよいよ1年半後に迫った創立100周年の記念事業の一環として2024年12月に開催した「京都の化学・化研の歴史」講演会からは、社会を支える技術は常に基礎科学研究の上に成り立っていることを改めて学びました。また、その研究のときどきにおいて大きな方向転換を受け入れる決断や、未知の領域へ飛び込む覚悟があったことを知ることもできました。これらは私たちがこれからの時代に向けて飛躍する際に大きな勇気を与えるものです。100年の節目を前に、改めて化学研究所の将来像を教職員・学生と一体となり議論し、未来の科学の発展を展望したいと考えています。
今年度は、栗原達夫、寺西利治の両副所長、小野輝男国際共同研究ステーション長をはじめ、ほとんどの所内委員会委員に留任してもらい、継続的な運営体制を維持する一方で、化学研究所の一層の発展と新たな未来へ向けての議論を本格的に開始することにしました。引き続き、皆様のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
2025年4月
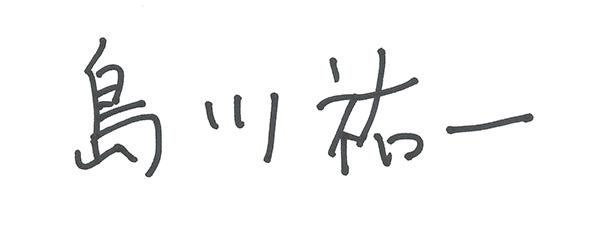
 京都大学 化学研究所
京都大学 化学研究所 国際共同利用・共同研究拠点
国際共同利用・共同研究拠点