

| 出席者 | 江崎 信芳 | (所長) |
| 佐藤 直樹 | (副所長) | |
| 時任 宣博 | (副所長) | |
| 長崎 順一 | (化研担当事務室長) |
掲載編 テーマ
「80周年を迎えて」
目次
■ 化研創立80周年を振り返って
■ 研究専念のできる場所
■ これからの化研
| 化研創立80年を振り返って |
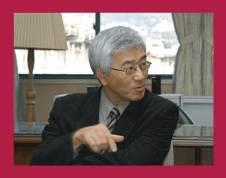 |
江崎 化研は今年80周年を迎えます。大学の附置研究所らしくなったのは昭和39年頃で、それまでは今でいうベンチャーラボラトリーの一種だったようですね。 時任 国策として、民間ではまだ難しくて作れないものを作る、そういう場所だったんですよね。 江崎 合成1号(ビニロン)が完成した頃は、ベンチャーラボラトリーとして非常に評価が高かった。けれど、名目上化研の所属になっているだけの方も多くて実動性が乏しかった。 |
|
時任 櫻田先生もビニロンの一件で化研の手柄のように言われますが、実態は他の大学籍が主でこちらに工場があるという具合でしたものね。湯川先生もそうです。 江崎 「これはなんとかしなければ」と立ちあがったのが内野先生や堀尾先生でした。熱意をもって取り組まれ、その後は武居三吉(さんきち)先生という方が、自らまず兼任を断って専任となり、専任の先生方が増えるように改善されたそうです。それなりの大きさもあって「化学」というくくりでまとまれるこの組織を、80年の歴史の中で勝ち取ってきた。改めて大したものだなと思いますね。ただ、現代のこの10年間とそれ以前とでは、時間の流れ方も化学の土壌も全く違います。特にこれからの10年間がどうなっていくか、単に大きいだけではだめですし、よく考えていかなければなりません。 時任 トップダウン的な発想が必要ですよね。 江崎 所長時代に強力なリーダーシップを発揮された堀尾先生ですが、一番ご尽力なされたのは、いい人を連れて来ることでした。関係のない先生には出て行ってもらい、いい人に来てもらう。説得材料としては、堀尾先生ご自身の資金力、すなわち金銭面での産業界からの支援をはじめ、学術的な面での高い評価があった。運営には所長個人の力や人柄も大事なのだなと思いました。人を動かそうと思えば、相当しっかりしないとね。 時任 法人化後、一年経って所長になられたわけですが、一番大事なのはそこでの対処の仕方でしょう。 |
|
|
佐藤 法人化で良くなったということはありますかね? あまりピンときませんね。 時任 正しく運用されれば、労働安全衛生面はよくなるでしょう。ですが、あまり杓子定規に民間のレベルを押し付けると大学の良さがなくなる。大学らしさを残した運用ができればね。法人化に伴う雑務や事務処理に追われて、京都大学の自由な学風さえ失われかねない雰囲気ですから。責任を課す分、自由度を与えてほしいですよね。 |
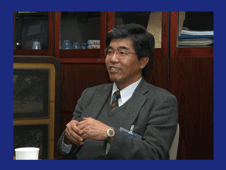 |
| 研究専念のできる場所 |
|
江崎 堀尾先生の頃は、大学院の指導ができるのは学部の教授だけで、化研の先生には認められていなかった。これについてまずご自身の工学部から大学院生を受け入れることができるように努力されたそうです。昭和28年頃のことですが、教育について学部の教授に重きが置かれるのは、今でも変わってないですね。 時任 われわれの担当は、各研究科の基幹講座に対する協力講座という補完的な立場ですものね。それぞれがバラバラで化研内の各研究室の教育寄与が異分野の人に必ずしも伝わってないのでしょう。 |
|
 |
佐藤 附置研の協力講座が認められたのは、おそらく化研あたりが最初ではないですか。 時任 少なくとも京大の中ではそうでしょうね。研究室個々のレベルは、皆さん各分野で活躍され、高いと思いますが、バラバラでは化研全体としてのアピール力が上がってこない。大きいだけというデパート型に行き着いてしまいます。 |
|
江崎 過日、「研究専念環境」という考え方が話題となっていましたが、研究科では学部生の授業や実習を抱えているし、学内で研究専念できる場所といえば研究所です。法人化体制のなかで、化研の良いところはどこか、他と何が違うのかを周囲に伝えていく必要が生じています。その場合「研究専念できる」というのも含まれると思うのです。化研には現在31人の教授とそれぞれ担当する研究室があります。これだけの規模があれば、「このグループは研究に、より専念させよう」ということを実現できるパラダイス的な場所にもなり得ます。 時任 そのためには、相当よく考え、理想的な人事をするための努力を惜しまないことでしょうね。研究専念できる立場が偏るとひがみが出て「何故われわれが支えなければならないのか、ノーだ」という反感意見が出やすくなります。制度的なものも含めて考えないとね。 江崎 ええ。化研の中の運営をどうするかは大事です。「化研全体で、誰もが例外なく研究専念する」という理解では前に進みません。有望な芽を徹底的に伸ばそうという考えを所属員一人ひとり全員が持って、全体でサポートするような体制。それこそ化研が果たさなければならない「研究専念環境づくり」での役割だと思うのです。 佐藤 ある程度は今の組織体制でもできるはずです。それを目指して先の改正に取り組んだところもあるわけですから。「物質創製化学研究系」をはじめとする5つの研究系というのは割合・・・ 時任 幅の広がりを持たせてありますよね。細部を実際にどうするかを立ち戻って考えやすい。 佐藤 ええ。一方で「先端ビームナノ科学センター」をはじめとする3つのセンターでは、特化した分野を必要な時期に力強く配置していけます。この「研究系」と「センター」のような、何らかの二重構造が必要だと思います。 江崎 お二人もこうやって副所長として研究以外の忙しい仕事をこなされているわけですけれども、「研究専念」って要するにどういうことだと思われますか? 時任 所長や副所長というのは管理運営上で必要なものですから別ですね。個々の研究者が抱える内外部評価の対象が多すぎて、報告書類の作成や伝票整理など、年に何度も課されるという多重業務が問題です。そういった現状をいかにして排除するかが「研究専念」できるかどうかのカギになるのではないでしょうか。 |
|
| 江崎 この人は頑張っているから、雑務をできる限り減らしてあげようとか、サポート体制も生まれますよね。特に若い先生には事務仕事にしばられず「研究専念」してもらいたい。
時任 京大にしても化研にしても大きくて長い時間を経てきていますから、歴史をちゃんと認識し、ある程度の準備期間をもって化研での実績につなげていってもらいたいですね。自分の研究に対する要求を述べるだけでは、所内でも学内でも相手にされないでしょう。研究所があまりに「研究専念」を主張しすぎるのも、研究科との壁を高くし、大学内の協力体制が壊れてしまいます。結果として「研究専念環境」ができる形がいいですよね。研究科と研究所がもっとコミュニケーションをとって、最もうまく機能するにはどうしたらいいかと、本気で考えるチャンネルがあればね。お互いに相手を思いやる余裕が欲しいですね。 |
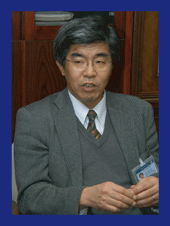 |
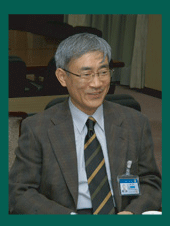 |
佐藤 研究科では研究専念というと、教育の義務を外して何年間か研究に専念することをいいます。ですから大学の中でいえば、化研はもう「研究専念」の体制に当然なっている、となるわけです。 時任 化研の教員すべてが「研究専念を」というと、教育する気がないととられてしまう危惧もあり難しいですね。ジェネレーションを限って、何か努力をする若手に「研究専念環境」を提供するような形などはどうでしょう。 江崎 「研究専念」ができるコアとか人とか場所を作りやすい仕組みがまず必要ですね。化研に対して学内から見ている人は「昔は貸しラボラトリーみたいな研究所だったけれど、それが今は研究科と実態はかわらない」というような印象や、「これからは大学発の発明・発見・産業化の時代、社会に対してもっとサービスすれば、京大にとっても有効なのに」というような見方もありえ得るんですよね。 |
|
時任 それには学内での人事交流が不可欠です。定期的な人事の際、学内の異動にも目を向けてみてはどうでしょう。親近感が増す上に、事情をお互いに理解できる。 江崎 まわりの目に迎合するのではなくて、化研はどんな場所かと問われたときに「ユニークな研究機構が育っているよ」という周知があると同時に、われわれも自負しないとね。安閑と胡座(あぐら)をかいていてはだめで、原点に返って、ここでしかできない研究をもっと意識してやる。先生がおっしゃった人事交流なんかも含めてね。ぼくらはトップとして、そのためにいい人を連れてくる。教育にももちろん目を向けながら、いい研究をここでやる。化研のなかに「育っているな〜」とゆっくりでも見えるような形でやっていけるかどうかがカギじゃないかなと思うんですよね。 時任 化研の一員であることを、プライドを持ってあちこちで自負できるような人が増えてほしいですよね。化学という分野に自分がいるということの意義と誇りを自問自答しながら、学内外でアピールできれば、われわれの目指している組織というものが意味をもってくるはずです。 佐藤 外から化研を見たときに、個人の名前が出てくる方はたくさんいらっしゃいます。でもその前に「化研の」と付く方が少ない気がします。 時任 その分野では有名なんですよね。その先生が例えば「京大の○○です」ではなく「化研の○○です」とアピールすれば化研の発展につながる。教授31名とそれぞれのラボがある。そこにいる人皆さんがプライドを持って、適度なアピールをお願いしたいですね。 |
|
| これからの化研 |
|
時任 研究所全体の雰囲気は決して悪くありません。ただ人事面や金銭面で将来に危機感を覚えます。あと建物の老朽化も懸念されます。80年の歴史があれば色んなものが古くなってきている。それに対しての対策が遅れているというのは否めないですね。 江崎 確かに老朽化していますが、それぞれの研究室内とか廊下とか、建物内はかなりきちっとしていますよね。 時任 ええ。学外から来客がいらっしゃったときに「古い建物だけどきれいにうまく使ってらっしゃいますね」という評価をいただきました。それに1研究室に対して、学生は少ないけれども面積が比較的広いので機器もある程度は置けるし、研究をするには恵まれています。良い意味での既得権を活かしつつ、いかに次世代につなげるインフラ整備ができるかが課題ですね。一所長の任期が、長くて3年という状況下では難しいですが、全学に常にアピールしていければ良いですね。大学の執行部がもう少し、この時期になったらこれをするとか、第一期、第二期、第三期の計画性のアウトラインだけでも示してくれれば対応しやすくなりますね。 江崎 先が見えないなかでどうしていくかというのは本当に困った状況です。自分たちでできるところはきちっとやろうという、研究にかける意思、意欲が不可欠です。 時任 もう一つ最近気になるのは、あまりにも連携連携という嵐が吹き荒れていること。「学内連携」「学外連携」と確かにそれは聞こえがいいですが、皆さんの目が外にばかり向いて、一番必要な化研の中での連携がおろそかになっている気がする。お互いの間にだんだん隙間風が吹き始めるという恐れもあります。何か本体のアイデンティティを保持していけるような求心力のあるシステムかイベントが欲しいですね。 江崎 現時点でいうなら「化研らしい融合的・開拓的研究」でしょうか。 時任 少しかけ離れた分野をお見合いさせてみるという実験ですよね。まだ始まって2年ですから、長い目で見守っていきたいです。 |
|
|
江崎 アクションが起こったというのはいいことですよね。かけがえのないものがそこから育つと思うんです。 佐藤 第一線の若い人たちが、お互い何かの機会に相談をしたり、そういう風潮を助長していくことは間違いないので、その点はとてもいいと思います。 江崎 融合というかお互いの結びつきが大切で、情報はできるだけオープンにして、「あれはいいなあ」というような関係を保っておく。一つの研究だけやっていれば安泰だというのではなく、常にほかの分野を見渡しながら、新しい研究を模索していくことが大事なのではないでしょうか。そのような中でいい研究というのは自ずと支持され認められて、生き残ってゆくと思います。 |
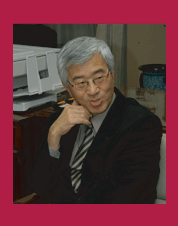 |